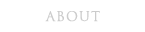2025年3月
ケヤキ材でハンドメイドルアーを作る
ケヤキの材料でルアーを作る
ケヤキ材の美しい木目を活かし、アルミホイル系を貼り仕上がりを良く見せる工夫などをして、見た目も良く、魚だけではなく、アングラーから見ても魅力的なルアーが作れます。 また重さを活かし、遠投性を重視、遠くに投げる際の【飛距離】が欲しい場合にも有利なルアーとなります。
作りたいルアーの目的や釣り場の環境に応じて、ケヤキ材の特徴をどのように活かすかを考えるのが最大のポイントです。
ケヤキ材のルアーは、全体の重さ【重心】を活かしたアクションや美しい外観を求めるものであれば、ケヤキは非常に魅力的な素材です。
作りたいルアーの目的や釣り場の環境に応じて、ケヤキ材の特徴をどのように活かすかを考えるのが最大のポイントです。
ケヤキ材のルアーは、全体の重さ【重心】を活かしたアクションや美しい外観を求めるものであれば、ケヤキは非常に魅力的な素材です。
お勧めのルアーは
ミノーやトップウォーター、クランクベイト、バイブレーションなどにお勧めで、なぜ ケヤキ材でルアーを作ることを勧めるか。 私が作ったルアーの種類、タイプやその時に感じたメリットやデメリットもご紹介します。
☆ ケヤキ材の特長を活かすルアー
主なルアーのタイプは、特にシンキングタイプで、フローティングも作れます。
☆ ケヤキ材で作るタイプやアクション
1. ミノー&ジャークベイト編
ケヤキの重さを活かしてシンキングミノーでの安定感が増します。
特に流れの速い川でもしっかりとしたアクションが出せる。
ケヤキの特徴的な重さを活かしてシンキングミノー(沈むタイプ)を作ると、その独自の重量感により水中での安定感が非常に高まります。このため、流れが速い川の中でもルアーがしっかりとしたアクションを維持できるという特長があります。つまり、水流による影響を受けにくく、思い通りの動きが再現しやすくなるのです。
特に流れの速い川でもしっかりとしたアクションが出せる。
ケヤキの特徴的な重さを活かしてシンキングミノー(沈むタイプ)を作ると、その独自の重量感により水中での安定感が非常に高まります。このため、流れが速い川の中でもルアーがしっかりとしたアクションを維持できるという特長があります。つまり、水流による影響を受けにくく、思い通りの動きが再現しやすくなるのです。
☆ スローリトリーブ時は滑らかな泳ぎで、リフト&フォールでは、フラッシング効果も期待できます。
スローリトリーブを行った際には、まるで本物の魚のような滑らかで自然な泳ぎを見せ、魚を誘うことができます。また 一方で、リフト&フォール(ルアーを上下に持ち上げるようなアクション)を沈ませる動きを活用すると、水中で光を反射しながら自然に揺れるフラッシング効果を発揮します。このフラッシング効果により、魚にとって非常に魅力的な視覚的アピールを生み出すことができます。
スローリトリーブを行った際には、まるで本物の魚のような滑らかで自然な泳ぎを見せ、魚を誘うことができます。また 一方で、リフト&フォール(ルアーを上下に持ち上げるようなアクション)を沈ませる動きを活用すると、水中で光を反射しながら自然に揺れるフラッシング効果を発揮します。このフラッシング効果により、魚にとって非常に魅力的な視覚的アピールを生み出すことができます。
☆ ケヤキ材の重量特性はミノーやジャークベイト系が良く、特にお勧めするのが、シンキング系のミノーやジャークベイト系です。特に流れの強い環境下でも適応力が高く、さまざまなアクションやリトリーブ方法に応じてその性能を十分に引き出すことが可能な、非常に優れたルアーとなります。
2. トップ、ペンシルベイト編
ケヤキ材で比較的細長いペンシルベイトにすると、ケヤキ材自体の重量感を活かし、ロングキャストが可能になる。
ケヤキ材を使用し、比較的細長い形状のペンシルベイトを作成することで、その特徴的な重量感を最大限に活用できます。この素材は重量感があるおかげで(ウェイトが小さくてもバランスが向上)キャスティングの際に遠くまで飛ばすことが可能になり、広範囲を効率的に攻めることができます。特にロングキャストが必要な場面や、広いフィールドでの釣りにおいては、大きなアドバンテージとなります。
☆ サーフェス系(表層)のトップウォータールアー
アクションとして、ウォーキング・ザ・ドッグのようなアクションがより魅力的になります。
ケヤキ材でのペンシルベイトはストレートな形のトップウォータールアーとして活躍します。
トップウォーターならではの特徴として、ウォーキング・ザ・ドッグと呼ばれるジグザグのアクションを行う際、その動きが非常に滑らかで、水面を滑っているような魅力的なアクションが出せます。特にケヤキ材でこのアクションは、他の素材とは異なり、水面で左右にスロースライドするような滑らかな動きを見せ、神経質な魚を効果的に誘うことができます。特にこの滑らかさは水面の「揺らぎや波紋」がとてもナチュラルに生み出され、魚にとって興味を引きやすい視覚的なアピールを強調します。
アクションとして、ウォーキング・ザ・ドッグのようなアクションがより魅力的になります。
ケヤキ材でのペンシルベイトはストレートな形のトップウォータールアーとして活躍します。
トップウォーターならではの特徴として、ウォーキング・ザ・ドッグと呼ばれるジグザグのアクションを行う際、その動きが非常に滑らかで、水面を滑っているような魅力的なアクションが出せます。特にケヤキ材でこのアクションは、他の素材とは異なり、水面で左右にスロースライドするような滑らかな動きを見せ、神経質な魚を効果的に誘うことができます。特にこの滑らかさは水面の「揺らぎや波紋」がとてもナチュラルに生み出され、魚にとって興味を引きやすい視覚的なアピールを強調します。
☆ ケヤキ材の特性として少し細長いデザイン
ペンシルベイトは、ロングキャスト能力に優れ、さらにスロートップウォーターでの操作性やアクションの魅力を引き出す、非常に実用的で効果的なルアーといえます。特にビックレイクなどの広い水域では水面での誘いがとても重要で必要なシチュエーションも多く、このケヤキ材ルアーがその真価を発揮します。
3. クランクベイト編
クランクベイトでは、ケヤキの硬さが耐久性を高めつつ、水中でのアクションもタイトからワイドまでと好みのアクションが出せるルアーができます。
ケヤキ材でクランクベイトを作ることで、その素材の硬さを最大限に活かすことができます。
ケヤキ材は非常に硬い性質を持っているため、ルアー自体の耐久性が高まり、ボトムコンタクトの際に激しいコンタクトがあっても損傷しにくく、長く使用できるという大きな利点もあります。また、その硬さは作る際に、水中でのタイトなアクションやワイドなアクションを演出させる事もでき、狙ったアクションを支える要因ともなります。
ケヤキ材は非常に硬い性質を持っているため、ルアー自体の耐久性が高まり、ボトムコンタクトの際に激しいコンタクトがあっても損傷しにくく、長く使用できるという大きな利点もあります。また、その硬さは作る際に、水中でのタイトなアクションやワイドなアクションを演出させる事もでき、狙ったアクションを支える要因ともなります。
☆ アクションはタイトからワイドまで
ルアーが小刻みに揺れるような動きのことで、これが魚にとって非常に魅力的な視覚的・動的なアピールとなります。また ワイドなアクションはルアーがゆっくりと左右に傾き、その際にキラキラとボディを光らせながら、視覚的にルアーの存在をアピールできます。特に深場を攻める際のビックリップのディープダイビングクランクを作れば、重さを活かしてディープレンジ攻略が想像以上に攻めやすくなります。
ケヤキ材の特性を活かすとディープレンジをターゲットとする深めのダイビングクランクを作ることができます。
この重さのおかげで、ルアーは素早く深い層へ到達しやすくなり、ディープレンジを効率的に攻めることが可能です。特に深い場所に生息する魚を狙う際には、この特性が非常に有効的になります。また 重さ、ウェイトバランスを適切に設計されたタイトなダイビング系クランクは、流れの強いエリアでも安定した動きを保ちながら魚を誘うこともできます。
ケヤキ材を使用したクランクベイトは、耐久性と機能性を兼ね備え、水中でのタイトやワイドなアクションを生み出しつつ、深い水域も効率よく攻略できます。
また少し流れがある浅いエリアでも使えるルアーで、特にビックリップで少し流れが速い場所やディープレンジを積極的に狙う釣りのシチュエーションでも、その性能を最大限に発揮するでしょう。
この重さのおかげで、ルアーは素早く深い層へ到達しやすくなり、ディープレンジを効率的に攻めることが可能です。特に深い場所に生息する魚を狙う際には、この特性が非常に有効的になります。また 重さ、ウェイトバランスを適切に設計されたタイトなダイビング系クランクは、流れの強いエリアでも安定した動きを保ちながら魚を誘うこともできます。
ケヤキ材を使用したクランクベイトは、耐久性と機能性を兼ね備え、水中でのタイトやワイドなアクションを生み出しつつ、深い水域も効率よく攻略できます。
また少し流れがある浅いエリアでも使えるルアーで、特にビックリップで少し流れが速い場所やディープレンジを積極的に狙う釣りのシチュエーションでも、その性能を最大限に発揮するでしょう。
4. バイブレーション編
特にバイブレーションルアーの場合、ケヤキの硬さと密度を利用して適度な重量感を持たせ、水中での振動やサウンドを強調できます。これは特にシンキングタイプとして広いエリアを効率よく探索することにも向いています。
☆ シンキング系バイブレーション
ケヤキ材、素材の重さを活かすためにも最適で人気があるルアーといえば、このタイプで、素材自体が重いから自然と沈む特性があるため、深いレンジや速い流れの中でしっかりと動き、狙いたい水深やレンジキープ性にも優れている効果的なルアーです。
ケヤキ材で作られた(シンキングタイプ)のバイブレーションは、ケヤキ材ルアーのなかでも、一番重さを最大限に活かすことができるルアーです。
その重量特性により、キャストから水中へ沈むスピードが速く、狙いたい深いレンジに素早く到達することが可能です。そのため、流れの速い(川や深場)をターゲットとする釣り場において、その性能を十分に発揮することができます。
とくに強い水流にも負けず安定して動き(フックとの擦れる音)サウンド効果もあり、複雑な環境でも確実にターゲットにアプローチ、アピールできる点が大きな利点です。 またシンキングバイブレーションの特長として、自然なフォールアクション(沈む際の動き)が魚にアピールしやすいことです。
このバイブレーションタイプのルアーは、沈む際に発揮される「フォールアクション」が非常にナチュラルで魅力的なことです。(フォールアクション)ルアーが水中で沈む際に起こる(動き)のことで、ケヤキ材の特性もあり、より自然な揺れや動きが再現されます。この動きが、水中にいる魚に対して大きな視覚的・動的アピールとなり効果を発揮します。そのため、魚が食いつくチャンス(時間)を大幅に増やすことが期待できます。
シンキングタイプのバイブレーションは、その重さを活かした深いレンジ攻略能力や、流れの速い環境下での安定した動作が特徴的です。さらに、素材の硬さとボディとフックの擦れるサウンドで、より自然で魅力的なフォールアクションへとつながります。全てがひとつとなり、魚へのアピール効果が高まり、特に深場や速い流れでの釣りにおいて非常に効果的な選択肢となるでしょう。
ケヤキ材で作られた(シンキングタイプ)のバイブレーションは、ケヤキ材ルアーのなかでも、一番重さを最大限に活かすことができるルアーです。
その重量特性により、キャストから水中へ沈むスピードが速く、狙いたい深いレンジに素早く到達することが可能です。そのため、流れの速い(川や深場)をターゲットとする釣り場において、その性能を十分に発揮することができます。
とくに強い水流にも負けず安定して動き(フックとの擦れる音)サウンド効果もあり、複雑な環境でも確実にターゲットにアプローチ、アピールできる点が大きな利点です。 またシンキングバイブレーションの特長として、自然なフォールアクション(沈む際の動き)が魚にアピールしやすいことです。
このバイブレーションタイプのルアーは、沈む際に発揮される「フォールアクション」が非常にナチュラルで魅力的なことです。(フォールアクション)ルアーが水中で沈む際に起こる(動き)のことで、ケヤキ材の特性もあり、より自然な揺れや動きが再現されます。この動きが、水中にいる魚に対して大きな視覚的・動的アピールとなり効果を発揮します。そのため、魚が食いつくチャンス(時間)を大幅に増やすことが期待できます。
シンキングタイプのバイブレーションは、その重さを活かした深いレンジ攻略能力や、流れの速い環境下での安定した動作が特徴的です。さらに、素材の硬さとボディとフックの擦れるサウンドで、より自然で魅力的なフォールアクションへとつながります。全てがひとつとなり、魚へのアピール効果が高まり、特に深場や速い流れでの釣りにおいて非常に効果的な選択肢となるでしょう。
☆ フローティング系バイブレーション
ケヤキ材を使ってフローティングバイブレーションルアーを作るには、浮力を補うために少し工夫が必要です。
フローティングタイプのバイブレーションルアーを製作する際には、他の軽量な木材と比べて重いため、そのままでは「浮力が不足」してしまう可能性があります。
たとえば、ルアーの内部をくり抜くことで全体の重量を軽減する方法が挙げられますが、これは木材の強度は保ちつつ、浮力を少し高めることはできますが、ルアーとして考えた時には、お勧めはできません。
なかでも、一番考えられることは、バルサ材のような軽い木材を組み合わせた(ハイブリッド構造)にするという方法もあります。
この構造にすることで、ケヤキの耐久性と浮力のバランスをうまく調整でき、より効果的なフローティングルアーを実現することも可能です。こうした工夫により、浮力を適切に調整できると(ルアーを水面で動かす動作)がより簡単になり効果的なルアーになります。
具体的には、水面近くでのキビキビとしたアクションや浮くチカラを利用して、浅場での使用や根掛かりなどの対策にもなり、水面上部の動き(アクション)がより自然に表現され、ケヤキ材特有の乾いた(サウンド)は魚を引き寄せる力が向上します。
水面近くにある障害物の周辺でも操作性が良くなることで、深場にいる魚を浮かせて誘うなどのアクションもできます。
ケヤキ材のフローティングバイブレーションは、工夫を施すことでその強度と魅力的なアクション性能を両立させることが可能です。水面下の釣りにおいて、独自の存在感があり、さまざまなシチュエーションで優れた効果を発揮する頼もしいルアーと言えるでしょう。
浮力さえ調整できれば、トップウォーターのようなアクションや障害物周辺に停止させてのアピール力も増します。
たとえば、ルアーの内部をくり抜くことで全体の重量を軽減する方法が挙げられますが、これは木材の強度は保ちつつ、浮力を少し高めることはできますが、ルアーとして考えた時には、お勧めはできません。
なかでも、一番考えられることは、バルサ材のような軽い木材を組み合わせた(ハイブリッド構造)にするという方法もあります。
この構造にすることで、ケヤキの耐久性と浮力のバランスをうまく調整でき、より効果的なフローティングルアーを実現することも可能です。こうした工夫により、浮力を適切に調整できると(ルアーを水面で動かす動作)がより簡単になり効果的なルアーになります。
具体的には、水面近くでのキビキビとしたアクションや浮くチカラを利用して、浅場での使用や根掛かりなどの対策にもなり、水面上部の動き(アクション)がより自然に表現され、ケヤキ材特有の乾いた(サウンド)は魚を引き寄せる力が向上します。
水面近くにある障害物の周辺でも操作性が良くなることで、深場にいる魚を浮かせて誘うなどのアクションもできます。
ケヤキ材のフローティングバイブレーションは、工夫を施すことでその強度と魅力的なアクション性能を両立させることが可能です。水面下の釣りにおいて、独自の存在感があり、さまざまなシチュエーションで優れた効果を発揮する頼もしいルアーと言えるでしょう。
浮力さえ調整できれば、トップウォーターのようなアクションや障害物周辺に停止させてのアピール力も増します。
ケヤキ材のルアーは良いルアーですが、プラスやマイナスもある。
☆ デメリット
1. 加工が難しい
ケヤキの硬さゆえに、削ったり切ったりする際に、普通の道具だと負担が大きいです。ある程度の適切な工具(鋭い刃物や電動工具)が必要になります。
2. 重すぎる場合がある
ルアーとしての重量が増す。特に浮力(フローティングルアーなど)には不向きな場合があります。コレはある程度作っていると(感覚や経験)でわかります。
3. 扱いにくさ
加工時に(割れ)やすい特性があり、適切な技術や材料の見立て(木目、木理)などが求められます。
4. コストが高い場合も
ルアー用のケヤキ材は質の良いもの(木目、木理)細かな物ほど値段が高いため、コストを抑えたい場合には選択が難しい場合があります。
☆ メリット
1. 耐久性が高い
非常に硬く、衝撃に強い木材です。そのため、使用頻度が高くても変形しにくく、長持ちするルアーが作れます。
2. 美しい木目
ケヤキ特有の独特な木目は、仕上げると高級感があり、見た目にも優れたルアーが作れるのが魅力です。逸品、一期一会のルアーになります。
3. 安定感のある動き
材料自体の重量があるため、水中での安定性が良く、泳ぎ方やアクションに説得力のあるルアーが作れます。
4. 加工後の質感
硬いながらも(磨くととても滑らかな仕上がり)となり、仕上げ加工後や紙ヤスリだけで(無塗装)とても美しくなる点が評価されます。
このような一見クセのあるケヤキ材ですが、購入から加工、仕上げまでとても手間のかかる材料ですが、手をかけたぶん、非常に綺麗で良いルアーに仕上がります。また 他の方の意見や先入観にとらわれず、ご自身で考えて楽しいオリジナルのハンドメイドルアー作りを楽しんでください。
ハンドメイドルアーにイチョウ材を
私が何故【イチョウ材】を使用してルアーを作るのかについて簡単な説明をいたします。
イチョウの木の特徴
イチョウを植えた後、最初の2年間は特にゆっくりと成長し、大きく開けた適切な場所を選び、手入れをきちんとしていれば、成長を早められる木だと言われています。
その成長のスピードは結果年齢に達するまでに早くても5〜6年、最盛期に達するまでには20年ほどかかり、植えてから約14年ほどで実がつき始める樹高で、成熟すると高さは約15 mから24 mになり、短い期間でも約10mを超えるほどの早いスピードで成長します 。
そのため、木目はヒノキなどの細かい木目とは異なり、大きく大胆な木目が特長で、イチョウの寿命は数百年とも数千年ともいわれています。
イチョウ材の何が良いか
ハンドメイドルアー作りでの【銀杏材】は加工がしやすく、美しい木目のルアーに仕上がる材料としてとても良い材料です。
特に細かい顔や鰓などの「デザイン重視」のルアー「ライトゲーム用」のルアーには凄く適しています。ただし、大物釣り【ビックソルトウォーターゲーム】のような丈夫なルアーを作りたい場合には、慎重に検討する必要があります。
それでも貴殿のような経験豊富で手先の器用な方、また素材選びに【こだわり】のある方でしたら、きっと銀杏材の素材を上手く生かし、素晴らしいデザインのルアーが作れると思います。
すでに具体的なデザインやアイディアがあれば、ぜひ挑戦してみてください。
ハンドメイドルアー作りには無限大の可能性があります。
このようにハンドメイドルアー作りに素晴らしい銀杏材料なのですが、材料の特性や使用にあたって、幾つかのメリットやデメリットもあります。
銀杏材でルアー作り
確実にプラスのメリットの方が多い素材だと考えられますが、ただし、何事にも万能ではなく、その特性を理解した上で上手に使うことが重要です。
※ プラスのメリット
1 加工のしやすさ
なんといっても、初心者から熟練者まで、扱いやすい木材であり、自由なデザインやアクションが可能です。
2 浮力が高い
軽量で浮力が強い特性から、トップウォータールアーや特に浅場で使用頻度の高いルアーには最適です。また ミノーなどでの水中でのジャークやトゥイッチアクションなどにも反応が良く、水中から水面へ浮上する時のゆらゆらと浮上するナチュラルなアクションも引き出しやすく、このアクションが、バスやトラウトなどの魚種にとも良い効果を発揮します。
3 ナチュラルな美観、造形美
木目が大きく美しい仕上がりの良さがあるため、見た目にこだわったハンドメイドルアーを製作する際に細かな細工、形状なども可能です。ハンドメイドルアーの良さでもある、リアルで細かな造形は、釣り仲間にも自慢できるクオリティなども実現できます。
銀杏材のメリットとデメリット
先ほども記載したように、名木材ですので、どうしても高価になってしまいます。 大切な材料をなるべく、無駄なく、上手に使用していただくために、私の経験から幾つかのメリットやデメリットも書き添えたいと思います。また参考にしていただければ、決して難しい材料では無いと言うことをご理解していただけると思います。
なお 付け加えるとすれば、今回の材料以外でも似たような素晴らしい材料は他にも沢山あります。 少しでも参考になれば嬉しいです。
※ メリット
1. 軽量で扱いやすい
銀杏材は軽量で加工しやすい木材で、削りやすく形を整えるのが簡単なので、初心者にも扱いやすい材料と言えます。
2. 吸水性が低い
銀杏材は「水を吸いにくい」性質があり、これはハンドメイドルアーで1番大切な事です。水中で使用する物ですから、傷や凹み等、またフィッシュコンタクト等の衝撃に対しても耐久性が大切です。
3. 柔らかくて衝撃に強い
銀杏材は適度な柔軟性を持ち、衝撃を吸収しやすいので、アクション時やフィッシュヒット時に割れやカケにくいなどの特徴があります。
4. 美しい見た目
銀杏材は木目が淡く均一で、塗装や仕上げを施すととても綺麗な仕上がりになります。また装飾性を重視したいルアー作りにも向いています。
※ デメリット
1. 強度がやや低い
銀杏材は軽量で柔らかい反面、密度が低いため、非常に強い衝撃や負荷には弱い場合があります。大型魚向けのルアーには適さないことも多くあります。
2. 耐久性
激しい環境「コンタクト」にさらされる場合には、ヒノキや他のハードウッド系に比べるとやや摩耗しやすい面があります。
3.浮力の調整
銀杏材は軽いため、浮力が高くなる傾向があります。沈むタイプのルアーを作る場合には、ウェイトを多く追加する必要が出てしまいます。
銀杏材のルアー適性
なんといってもイチョウ材の軽さと加工のしやすさと水中での安定性に基づいては太鼓判を押しております。
各種魚種
1. バス釣りルアー
☆ トップウォータールアー
銀杏材の軽さと高い浮力が、ポッパーやペンシルベイトなどのトップウォータールアーに適しています。水面でのアクションがスムーズで、魚にアピールしやすい特性があります。
☆ クランクベイト
銀杏材の加工しやすさを活かして、流線型のクランクベイトを製作するのに向いています。軽量なのでシャローエリア(浅場)での操作がしやすくなります。
2. 渓流トラウト用ルアー
☆ ミノー系、トゥイッチアクションをメインに小型で軽量なルアーを作る場合、銀杏材はとても適しています。特に渓流で多く使用する小型のミノーでの釣り場では、ナチュラルなアクションとトゥイッチアクションが実現できます。水中での耐水性や安定性はトラウトルアーに適しています。
3.ソルトライトゲーム
メバリングやアジングで銀杏材特有のポテンシャルを発揮できます。オモリ、ウェイト加工の自由度を活かし、小型のルアー(スローシンキングミノー)を製作できます。これらは夜釣りなどの発光系カラーで、特にライトタックルの使用に適していると考えております。
以上のようなことで、銀杏材はメリットを生かせるポイントが多くあり、軽量で高い浮力のルアー材料として最適で、特にトップウォータールアーやフローティングタイプで、比較的軽量のトラウトやライトゲームルアーに向いています。
また繊細なアクションも演出しやすく、【リアクションバイト】を誘発するような少し派手なアクションを求めるルアー制作が得意だと感じました。 ただし 強度がやや低めなので【力の強い魚種】ヘビーなタックルでのルアーにはあまり適していないと感じました。
ご自身のフィッシングスタイルや狙う魚種に応じて考える必要は多く有ります。
また銀杏材の特性を活かしたデザイン、形状も考える方が無難で、なるべくベストに近いルアー作りを研究開発してください。
問題点や制作課題
銀杏材は軽さを優先した分、強度や耐久性がヒノキやカリンなどのハードウッドには劣ります。そのため、大型のソルトウォータールアーや激しい環境下で使用する場合には注意が必要です。
適切なウェイト調整や溶剤等によるコーディング、下地から【アンダー&トップハードコーディング】の技術が求められます。
このルアーに採用
先にものべましたが、銀杏材は特にバス釣りでの、トップウォーターやミノー&ジャークベイト系での使用やソルトのライトトップウォーターゲームや渓流でのトラウトゲームに適しております。
その一方で、このようなスタイルの中でも、強度が求められるヘビーカバーのコンタクトが多い場所や渓流等で、ゴツゴツとした石や岩などが多いエリアなどでは渓流釣り、バス釣に限らず他の材を検討すべきだと感じております。
以上の事から素材選びの特性を良く理解し、最大限に利用して制作することができる貴殿でしたら、銀杏材を使ったルアーは、次回制作のルアー開発、制作が進む材料になる事でしょう。
同じ様な説明か繰り返しになっておりますが、高価な名木材料ですから、何度も書き添えたこともご理解くださいね。
バルサ材はルアー作りに不向き
実はバルサ材はルアー作りに不向き
ルアー制作の木材として最も一般的なのがホームセンターなどで購入できる「バルサ材」から始める方が多いと思いますが、私の経験からいえば、ホームセンター等で簡単に入手できる【軽く、柔らかいバルサ材】はルアー作りで、【初心者向け】というのは大きな間違いです。
軽く柔らかいバルサ材はなぜ不向き
ホームセンター等で売られているバルサ材は「軽く柔らかいバルサ材」で、材料の比重が軽いという事は、イコール【浮力がとても強い】ということになります。また浮力のある材料を使用すると、水面に浮いた時や水中で左右上下に動いたとき、どちらかに傾く力が強く、「ウェイト設定」が難しく、設定がとても「シビア」になるということです。
そのためハンドメイドルアー作りの経験数があまり無い初心者には向いていないと言う事で、初心者がホームセンターなどのバルサ材でルアー作りを始めた時のメリットは、ボディの加工が簡単にできるという程度のメリットしか無いというわけです。
どんなバルサ材でもコーティングが不可欠
一般的にバルサ材で作ったルアーはレスポンスが良く、アクションはクイックになると言われますが、バルサ材を使うということは「ソフト系でもハード系でも」水の侵入や衝撃等の為にデッピングコートが必要になり、その工程で下地、カラーリングやトップコーティング等の溶剤、薬品でルアーがどうしても重くなります。この事を理解した上でも、初心者にはもう少し大切な事があります。それは材料が柔らかいから「コーティング」を厚く何度も重ねてしまいぶ厚くなる事や、その反対に、「コーティングが薄く」なっていたりと、本来、水の侵入から「ボディを保護するため」や「バルサ材の強度を上げる等」の作業なのですが、その繰り返しの作業自体が上手くできずに終わっているという事も良くあります。材料が木材ということからも、ボディを保護するために繰り返さなければならない作業で間違いないのですが、このぶ厚いコーティングは、ルアー全体のウェイトが重くなってしまうという事で、それは「デメリット」になり、バルサのメリットでもある「クイックなアクションやレスポンス」を下げるという結果となります。
時間をかけて制作したルアーを保護するための、防水加工やデッピンクコート、下地、トップコーティング等でルアーが重くなり、最初に考えていたアクションが出せず、本末転倒の結果となってしまいます。
多くの方がバルサ材を身近で、最も簡単に使える材料として紹介していますが、軽く、柔らかいバルサ材はその制作工程について、どう考えてもルアー作りの「初心者向けの材料だとは言えない」と言うことです。初心者の方は、下地のコーティングやウェイト設定がシビアで難しい材料なので【柔らかい材料や軽い材料】でのルアー作りは、むしろ経験が豊富な【上級者向け】のルアー材料だといえます。
一番硬くて重いバルサ材
バルサ材で作ったルアーは「レスポンスが良くクイックなアクションになる」と思われがちですが、むしろ ほかの材料、比重がある木材の方が、良いアクションを出しやすいということが多くあります。
なので【敢えてバルサ材にこだわる必要は全くない】と言うことです。それでもハードバルサ材の購入先が見つからない場合には、ホームセンターで数十枚の中から「一番硬く重いバルサ材」を選んでください。
それが一番良い結果となります。